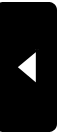2015年01月04日
琉球・奄美の世界自然遺産登録について
最近、あらゆる場所で「世界自然遺産登録」という言葉を聞く機会が増えた。
しかし、ぶっちゃけて話をすると、ワンは、世界自然遺産登録の意味が、よくわかっていない。もっと正確に表現すると「奄美が世界自然遺産登録された場合のメリット・デメリットというものを理解していない」のである。さらには、ほとんどのシマンチュが、ワンと同様に「世界自然遺産登録の意味を理解していない」もしくは「関心がない」のではないだろうか?
こんな状態で世界自然登録の話を進めて良いものか?・・・そんな素朴な疑問を抱えているので、今日は、少し掘り下げて考えてみたいと思う。

このキレイな海を、後世に残すために、きちんと考えたいですな
というわけで、いろいろ調べてみると、興味深い資料を発見することが出来た。
早稲田大学文学部ラオス地域人類学研究所所長の西村正雄氏が、2002年6月24日に行った「ユネスコ世界遺産の光と影」という講演の記録である。
DCC 2002年度 Breakfast Salon 第1回
http://www.waseda.jp/dcc/3rd/breakfast1.html
これは、世界自然遺産選定に関わっている教授が示しているもので、世界自然遺産というシステムが出来上がった経緯、世界自然遺産になることのメリット・デメリット、世界自然遺産登録を目指すにあたってやるべきこと、一読しただけでも「なるほど」と納得してしまう内容である。
全文は、リンク先で確認していただくとして、ここでは、ワンが気になったところを抽出してみたい。
メリット1:
世界的な視点になるということで世界の人々が注目する。それゆえに容易に壊したりいじったりできなくなる。なので遺産を守ることが出来る。
メリット2:
数多くの人々に資産の価値が知られるようになる。
メリット3:
観光開発に伴う経済的な効果が非常に大きい。
デメリット1:
遺産登録される際の条件に「美的条件」という項目があるが、世界で多様な価値基準がある中で、整合性を整えるのが難しい。
デメリット2:
経済的なメリットが、遺産をずっと先祖から守ってきた、地元の人々へ還元されない。
デメリット3:
ユネスコは、世界自然遺産に登録しっぱなしで、あとは、それぞれの遺産があるコミュニティーと国が世話してくれという、突き放したところがある。
遺産を守るために必要なことは「研究と教育」である。
1.遺産になる前と、なった後の調査をして、その研究結果を、しっかりと地元に還元する。
2.地元の政府関係者や遺産を守ってきた地元住民に「自分たちが持っているものの価値」を教える。
3.遺産を守る立場の地元住民に「世界自然遺産という新たな価値がどういうものなのか」を教える。
4.遺産を守る立場の地元住民に「新たな価値がついた遺産をどうしたらいいのか」というトレーニングを行う。
しかし、残念ながら、ここ奄美では「すでに世界自然遺産になった地域の調査結果が具体的に示されたことがない」し、遺産を守ってきた地元住民に対して「自分たちが持っているものの価値」について教育されたこともないし、「世界自然遺産という価値が付いた後に、地元住民がすべきこと」も提示されたことがない。だから、地元住民が無関心なまま、政治家や行政だけで「世界自然遺産登録」の話が進んでいるような印象を持たざるを得ない。
わたしたちは「奄美の自然は世界遺産となるべき貴重なもの」だということは漠然と感じている。しかし、心の底から、それを意識していないから、ゴミのポイ捨ては後を絶たないし、貴重な植物の伐採も行う者がいるのではないだろうか?
世界自然遺産登録を本気で目指すのであれば、地元住民が本気になる必要があり、そのためには住民に対する「徹底的な情報公開」と「教育」が必要なんだと思う。これなしで話を進めていけば、あとになって「こんなはずじゃなかった」という事態になり、そのときは誰も責任を取れないという最悪の状態になることが予想される。
奄美の貴重な自然は大切な宝である。しかし、私たちのものではない。私たちが「先人から預かって、後世へ引き継ぐまでの間、一時的に管理をゆだねられているだけ」である。そういう意識を持てば、世界自然遺産登録については、もっと慎重にならざるをえないと思う。そして、今こそ、琉球と奄美全体で、住民レベルで議論を重ねるべきだと思う。
世界自然登録を目指す立場の方々におかれましては、いまいちど「研究と教育」を丁寧に行っていただきたいと、心よりお願いします。
しかし、ぶっちゃけて話をすると、ワンは、世界自然遺産登録の意味が、よくわかっていない。もっと正確に表現すると「奄美が世界自然遺産登録された場合のメリット・デメリットというものを理解していない」のである。さらには、ほとんどのシマンチュが、ワンと同様に「世界自然遺産登録の意味を理解していない」もしくは「関心がない」のではないだろうか?
こんな状態で世界自然登録の話を進めて良いものか?・・・そんな素朴な疑問を抱えているので、今日は、少し掘り下げて考えてみたいと思う。
このキレイな海を、後世に残すために、きちんと考えたいですな
というわけで、いろいろ調べてみると、興味深い資料を発見することが出来た。
早稲田大学文学部ラオス地域人類学研究所所長の西村正雄氏が、2002年6月24日に行った「ユネスコ世界遺産の光と影」という講演の記録である。
DCC 2002年度 Breakfast Salon 第1回
http://www.waseda.jp/dcc/3rd/breakfast1.html
これは、世界自然遺産選定に関わっている教授が示しているもので、世界自然遺産というシステムが出来上がった経緯、世界自然遺産になることのメリット・デメリット、世界自然遺産登録を目指すにあたってやるべきこと、一読しただけでも「なるほど」と納得してしまう内容である。
全文は、リンク先で確認していただくとして、ここでは、ワンが気になったところを抽出してみたい。
メリット1:
世界的な視点になるということで世界の人々が注目する。それゆえに容易に壊したりいじったりできなくなる。なので遺産を守ることが出来る。
メリット2:
数多くの人々に資産の価値が知られるようになる。
メリット3:
観光開発に伴う経済的な効果が非常に大きい。
デメリット1:
遺産登録される際の条件に「美的条件」という項目があるが、世界で多様な価値基準がある中で、整合性を整えるのが難しい。
デメリット2:
経済的なメリットが、遺産をずっと先祖から守ってきた、地元の人々へ還元されない。
デメリット3:
ユネスコは、世界自然遺産に登録しっぱなしで、あとは、それぞれの遺産があるコミュニティーと国が世話してくれという、突き放したところがある。
遺産を守るために必要なことは「研究と教育」である。
1.遺産になる前と、なった後の調査をして、その研究結果を、しっかりと地元に還元する。
2.地元の政府関係者や遺産を守ってきた地元住民に「自分たちが持っているものの価値」を教える。
3.遺産を守る立場の地元住民に「世界自然遺産という新たな価値がどういうものなのか」を教える。
4.遺産を守る立場の地元住民に「新たな価値がついた遺産をどうしたらいいのか」というトレーニングを行う。
しかし、残念ながら、ここ奄美では「すでに世界自然遺産になった地域の調査結果が具体的に示されたことがない」し、遺産を守ってきた地元住民に対して「自分たちが持っているものの価値」について教育されたこともないし、「世界自然遺産という価値が付いた後に、地元住民がすべきこと」も提示されたことがない。だから、地元住民が無関心なまま、政治家や行政だけで「世界自然遺産登録」の話が進んでいるような印象を持たざるを得ない。
わたしたちは「奄美の自然は世界遺産となるべき貴重なもの」だということは漠然と感じている。しかし、心の底から、それを意識していないから、ゴミのポイ捨ては後を絶たないし、貴重な植物の伐採も行う者がいるのではないだろうか?
世界自然遺産登録を本気で目指すのであれば、地元住民が本気になる必要があり、そのためには住民に対する「徹底的な情報公開」と「教育」が必要なんだと思う。これなしで話を進めていけば、あとになって「こんなはずじゃなかった」という事態になり、そのときは誰も責任を取れないという最悪の状態になることが予想される。
奄美の貴重な自然は大切な宝である。しかし、私たちのものではない。私たちが「先人から預かって、後世へ引き継ぐまでの間、一時的に管理をゆだねられているだけ」である。そういう意識を持てば、世界自然遺産登録については、もっと慎重にならざるをえないと思う。そして、今こそ、琉球と奄美全体で、住民レベルで議論を重ねるべきだと思う。
世界自然登録を目指す立場の方々におかれましては、いまいちど「研究と教育」を丁寧に行っていただきたいと、心よりお願いします。