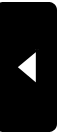2014年01月18日
118番の日
ヤーマン。バナナマフィンだす。
本日は「118番の日」だそうです。・・・っち言われても「118番っち何?」という人、多数じゃないでしょうか?はいはい。わかるわかる。ワンもそうだったの。それがね、ドゥシが関係者になったので、知ることになったわけ。
というわけで、118番の日とは何か?といいますと・・・
海上保安庁への緊急通報用電話番号が「118」で、「118番の日」とは、この緊急番号を広く知ってもらうために海上保安庁が2011(平成23)年から実施してるものなんですねぇ。
警察は110番、救急は119番、海上保安が118番、なわけです。

てなわけで
海の「もしも」は118番
詳しくは、海上保安庁のホームページをチェケラッチョ。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/joho/tel118/index.htm
みなさま、周知をお願いします。
・・・竜太さん、こんな広報でよろしかったかい???
本日は「118番の日」だそうです。・・・っち言われても「118番っち何?」という人、多数じゃないでしょうか?はいはい。わかるわかる。ワンもそうだったの。それがね、ドゥシが関係者になったので、知ることになったわけ。
というわけで、118番の日とは何か?といいますと・・・
海上保安庁への緊急通報用電話番号が「118」で、「118番の日」とは、この緊急番号を広く知ってもらうために海上保安庁が2011(平成23)年から実施してるものなんですねぇ。
警察は110番、救急は119番、海上保安が118番、なわけです。

てなわけで
海の「もしも」は118番
詳しくは、海上保安庁のホームページをチェケラッチョ。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/joho/tel118/index.htm
みなさま、周知をお願いします。
・・・竜太さん、こんな広報でよろしかったかい???
2014年01月17日
湾岸戦争開戦の日
ヤーマン。バナナマフィンだす。
1991年1月17日。アメリカ軍をはじめとする多国籍軍がイラクへの空爆を開始し、湾岸戦争が開戦しました。
当時、ワンは21歳。日本中がバブルでお祭り騒ぎだった中、金はないけど時間はたっぷりあったので、このニュースをテレビにかじりついて見ていた記憶があります。
ワンの年代はベトナム戦争の記憶はないけれども、その後の、イランイラク戦争とか、PLOがどーのこーのとか、アラファト議長がナントカカントカとか、ホメイニ師のヒゲは立派だなとか、そんなこんなの記憶はあるわけです。
しかし、この湾岸戦争の映像は、本当に衝撃でした。アマクマで色々な人が発言していますが、ワンも「ゲームの映像を見てるみたい」というのが正直な感想だったのです。それまでの戦争のイメージとは明らかに違ったのでした。
でもね・・・
実際には、戦争っちば、何も変わらないのよね。武器や、戦闘方法や、戦術や、そのようなものは時代と共に変化しているんだけど、結局は「人間と人間が殺し合う行為」なんですよね。
で
こういうことを書いちゃうと、昔は「そーだそーだ」と支持される感じだったのですが、最近では「左寄りだな」みたいなご意見をいただくことが増えてきた気がします。国全体が右傾化しているというのは言いすぎかもしれませんが、国を愛する気持ちを表現する方法として「国を守るために」という大義のもと「憲法9条改正」なんてことが真剣に話し合われようとしています。
まま、主義・主張は人それぞれなので、それは尊敬したいと思うのですが、戦争に関しては、ワンは、どうしても気持ちが変わることはありません。
人と人が殺し合うことは、あってはならないことです。
1991年1月17日。アメリカ軍をはじめとする多国籍軍がイラクへの空爆を開始し、湾岸戦争が開戦しました。
当時、ワンは21歳。日本中がバブルでお祭り騒ぎだった中、金はないけど時間はたっぷりあったので、このニュースをテレビにかじりついて見ていた記憶があります。
ワンの年代はベトナム戦争の記憶はないけれども、その後の、イランイラク戦争とか、PLOがどーのこーのとか、アラファト議長がナントカカントカとか、ホメイニ師のヒゲは立派だなとか、そんなこんなの記憶はあるわけです。
しかし、この湾岸戦争の映像は、本当に衝撃でした。アマクマで色々な人が発言していますが、ワンも「ゲームの映像を見てるみたい」というのが正直な感想だったのです。それまでの戦争のイメージとは明らかに違ったのでした。
でもね・・・
実際には、戦争っちば、何も変わらないのよね。武器や、戦闘方法や、戦術や、そのようなものは時代と共に変化しているんだけど、結局は「人間と人間が殺し合う行為」なんですよね。
で
こういうことを書いちゃうと、昔は「そーだそーだ」と支持される感じだったのですが、最近では「左寄りだな」みたいなご意見をいただくことが増えてきた気がします。国全体が右傾化しているというのは言いすぎかもしれませんが、国を愛する気持ちを表現する方法として「国を守るために」という大義のもと「憲法9条改正」なんてことが真剣に話し合われようとしています。
まま、主義・主張は人それぞれなので、それは尊敬したいと思うのですが、戦争に関しては、ワンは、どうしても気持ちが変わることはありません。
人と人が殺し合うことは、あってはならないことです。
2014年01月16日
藪入り
ヤーマン。バナナマフィンだす。
今日は「藪入り」という日なんだそうですが、藪入りっち知ってますか?
というわけで、この「藪入り」をウィキペディアさんで調べたところ「商家などに住み込み奉公していた丁稚や女中など奉公人が実家へと帰ることのできた休日」と記載されてました。1月と7月の16日が「藪入り」とされ、小正月(1月15日)とお盆(7月15日)にあわせて実家へ戻ることができたようなんですね。

東海道五十三次の日本橋 江戸の活気が伝わる名画ですな♪
あらら。なんだかステキな日じゃないの♪と思いつつ、さらに調べますと、落語の演目に「藪入り」というのがありました。
お♪ その名前は聞き覚えがあるぞ♪・・・というわけで、またまた ウィキペディアさん で調べてみますと、次のようなあらすじが紹介されてました。
住み込みで奉公をする子供が一日だけ親元へ帰ることが許される藪入りの日。門前で立派に挨拶をする様子を見て、我が子の成長ぶりに両親は感涙する。そして今日のために考えていた我が子へのもてなしとして、お祭りへ連れて行ったり、好物を食べさせたりすることを考えるが、その前にまずは湯屋へ汗を流しに行かせると、子供が紙入れを忘れている。その妙な膨らみに違和感を覚え、母親が中を見ると、紙入れの中には15両もの大金が入っていた。奉公先の小遣いだと考えるのにはあまりにも高額なため、二人は亀吉が何か悪事に手を染めたのではという疑念を抱き、とりあえず我が子の帰りを落ち着いて待とうということになるが、待つ時間が苛立ちを募らせ、喧嘩っ早い職人肌の父親は帰ってきた亀吉を有無を言わさず殴り飛ばして、なんで悪事になんか手を染めたんだと泣きながら問いただすと、亀吉はその15両は悪事で手にした金ではないと答える。憤る父を制止し、母親がじゃあどうやって手にした金なのかと聞くと、なんでも巷で流行るペストの予防のためにお役所が子供にねずみ取りをさせ、その鼠の懸賞で手にした金で、今日の藪入りのために預かっていた番頭さんから返してもらってきたところなのだと言う。我が子が悪事に走ってなかったことを知ると共に、我が子の強運を褒め讃え、父親は「これもご主人への忠(チュウ)のおかげなんだ」と言うのであった。
うーん。ステキな人情噺でございます。40歳を過ぎてから、めっぽう涙もろくなってしまったワタクシめ、あらすじを読んだだけで目頭が熱くなってしまいました。
で・・・
ここで終われば、めでたしめでたしなんですけども、ここにきて、ワンの目に留まった気になるワードがございました。
この「藪入り」という落語は「鼠の懸賞」という話を改作したものなんだそうです。さらには「鼠の懸賞」という話も改作で出来上がったもので、もともとの話は「お釜さま」という話であったわけです。
はい。ここで、カンの鋭い人は気づいたかもしれませんね。この元々の「お釜さま」という話は、レゲエ業界でいうところの「バティマン」の話なんです。・・・というわけで、そのあらすじをウィキペディアさんからご紹介すると
ある店の番頭が、同じ奉公人仲間の小僧をもてあそんでいたが、その代償として金を与えていた。さて、住み込みの奉公人でも1日だけ親元に帰ることができる藪入りの日。例のあわれな小僧も、両親が待ちわびる実家へ帰っていった。門口で立派に挨拶する小僧。両親はわが子の成長ぶりに感心し、とりあえず汗を流してやろうと、子供を湯屋へやる。ところが、残された子供の紙入れ(財布)の中を見た母は、中に大金が入っていることに驚く。奉公先での小遣いとは考えられず、魔がさしたのでは、と気をもみ出す。わが子を信じろと妻を叱り付ける父親も、結局は帰ってきた子供を殴りつけてしまう。「盗んだんじゃねえ」という息子は、番頭との関係を説明する。オチは父親「お釜(上)さまのおかげだ」
日本の習俗の中には衆道というのがあったのは知識として知ってはいましたが、それが落語になって、しかも一般的に受け入れられていたものだとはオドロキでした。
というわけで、現代に生まれて良かったわ・・・と胸をなでおろしたワタクシめでした。
おあとがよろしいようで。
今日は「藪入り」という日なんだそうですが、藪入りっち知ってますか?
というわけで、この「藪入り」をウィキペディアさんで調べたところ「商家などに住み込み奉公していた丁稚や女中など奉公人が実家へと帰ることのできた休日」と記載されてました。1月と7月の16日が「藪入り」とされ、小正月(1月15日)とお盆(7月15日)にあわせて実家へ戻ることができたようなんですね。

東海道五十三次の日本橋 江戸の活気が伝わる名画ですな♪
あらら。なんだかステキな日じゃないの♪と思いつつ、さらに調べますと、落語の演目に「藪入り」というのがありました。
お♪ その名前は聞き覚えがあるぞ♪・・・というわけで、またまた ウィキペディアさん で調べてみますと、次のようなあらすじが紹介されてました。
住み込みで奉公をする子供が一日だけ親元へ帰ることが許される藪入りの日。門前で立派に挨拶をする様子を見て、我が子の成長ぶりに両親は感涙する。そして今日のために考えていた我が子へのもてなしとして、お祭りへ連れて行ったり、好物を食べさせたりすることを考えるが、その前にまずは湯屋へ汗を流しに行かせると、子供が紙入れを忘れている。その妙な膨らみに違和感を覚え、母親が中を見ると、紙入れの中には15両もの大金が入っていた。奉公先の小遣いだと考えるのにはあまりにも高額なため、二人は亀吉が何か悪事に手を染めたのではという疑念を抱き、とりあえず我が子の帰りを落ち着いて待とうということになるが、待つ時間が苛立ちを募らせ、喧嘩っ早い職人肌の父親は帰ってきた亀吉を有無を言わさず殴り飛ばして、なんで悪事になんか手を染めたんだと泣きながら問いただすと、亀吉はその15両は悪事で手にした金ではないと答える。憤る父を制止し、母親がじゃあどうやって手にした金なのかと聞くと、なんでも巷で流行るペストの予防のためにお役所が子供にねずみ取りをさせ、その鼠の懸賞で手にした金で、今日の藪入りのために預かっていた番頭さんから返してもらってきたところなのだと言う。我が子が悪事に走ってなかったことを知ると共に、我が子の強運を褒め讃え、父親は「これもご主人への忠(チュウ)のおかげなんだ」と言うのであった。
うーん。ステキな人情噺でございます。40歳を過ぎてから、めっぽう涙もろくなってしまったワタクシめ、あらすじを読んだだけで目頭が熱くなってしまいました。
で・・・
ここで終われば、めでたしめでたしなんですけども、ここにきて、ワンの目に留まった気になるワードがございました。
この「藪入り」という落語は「鼠の懸賞」という話を改作したものなんだそうです。さらには「鼠の懸賞」という話も改作で出来上がったもので、もともとの話は「お釜さま」という話であったわけです。
はい。ここで、カンの鋭い人は気づいたかもしれませんね。この元々の「お釜さま」という話は、レゲエ業界でいうところの「バティマン」の話なんです。・・・というわけで、そのあらすじをウィキペディアさんからご紹介すると
ある店の番頭が、同じ奉公人仲間の小僧をもてあそんでいたが、その代償として金を与えていた。さて、住み込みの奉公人でも1日だけ親元に帰ることができる藪入りの日。例のあわれな小僧も、両親が待ちわびる実家へ帰っていった。門口で立派に挨拶する小僧。両親はわが子の成長ぶりに感心し、とりあえず汗を流してやろうと、子供を湯屋へやる。ところが、残された子供の紙入れ(財布)の中を見た母は、中に大金が入っていることに驚く。奉公先での小遣いとは考えられず、魔がさしたのでは、と気をもみ出す。わが子を信じろと妻を叱り付ける父親も、結局は帰ってきた子供を殴りつけてしまう。「盗んだんじゃねえ」という息子は、番頭との関係を説明する。オチは父親「お釜(上)さまのおかげだ」
日本の習俗の中には衆道というのがあったのは知識として知ってはいましたが、それが落語になって、しかも一般的に受け入れられていたものだとはオドロキでした。
というわけで、現代に生まれて良かったわ・・・と胸をなでおろしたワタクシめでした。
おあとがよろしいようで。
2014年01月15日
小正月
ヤーマン。バナナマフィンだす。
本日 1月15日 は、小正月だす。
小正月になると奄美ではナリモチを飾って、家内安全や五穀豊穣を祈願するわけです。

奄美パークさんのナリモチ
が!!!
我が家では、ナリモチを飾ったことがありません。ちゅうか、実家ではやってたのですよ。それが、実家を出て一人暮らしを始めてからは「メンドがクサイ」という理由だけでやってこなかったわけです。
これは、個人的には大きな反省点であるわけです。なぜなら、この年になって、島のこういった行事の大切さが身に沁みてわかるようになってきたからです。島で生まれ島で育ったはずのワンが島の心を忘れてしまっている気がして、それがとても後ろめたいのです。
というわけでそこらへんの反省も含め、今年はナリモチを飾ろうかなあ?と思います。
しかーーーし!! ここでまた一つの疑問が・・・。
通常、小正月というのは、旧暦の1月15日でやってたように思います。
じゃあ、今年の旧暦の1月15日はいつなのか?と調べてみましたら、新暦の2月14日になってました。
ということは、今日は本来の小正月じゃないわけです。
じゃあ、今日、小正月を祝うのは、なんか違うくね? という考えも頭をめぐるわけです。
しかし、島のアマクマの商店では「ナリモチ」売りまくってましたよ。ナリモチを刺す「ブブの木」も売ってましたよ。ちゅうことは、小正月については「新暦で行うのが、今のトレンド」みたいになってんの?
う~~~ん。よくわからない状況になっておりますが、いえることは一つ
今年はナリモチ飾ります!!
本日 1月15日 は、小正月だす。
小正月になると奄美ではナリモチを飾って、家内安全や五穀豊穣を祈願するわけです。

奄美パークさんのナリモチ
が!!!
我が家では、ナリモチを飾ったことがありません。ちゅうか、実家ではやってたのですよ。それが、実家を出て一人暮らしを始めてからは「メンドがクサイ」という理由だけでやってこなかったわけです。
これは、個人的には大きな反省点であるわけです。なぜなら、この年になって、島のこういった行事の大切さが身に沁みてわかるようになってきたからです。島で生まれ島で育ったはずのワンが島の心を忘れてしまっている気がして、それがとても後ろめたいのです。
というわけでそこらへんの反省も含め、今年はナリモチを飾ろうかなあ?と思います。
しかーーーし!! ここでまた一つの疑問が・・・。
通常、小正月というのは、旧暦の1月15日でやってたように思います。
じゃあ、今年の旧暦の1月15日はいつなのか?と調べてみましたら、新暦の2月14日になってました。
ということは、今日は本来の小正月じゃないわけです。
じゃあ、今日、小正月を祝うのは、なんか違うくね? という考えも頭をめぐるわけです。
しかし、島のアマクマの商店では「ナリモチ」売りまくってましたよ。ナリモチを刺す「ブブの木」も売ってましたよ。ちゅうことは、小正月については「新暦で行うのが、今のトレンド」みたいになってんの?
う~~~ん。よくわからない状況になっておりますが、いえることは一つ
今年はナリモチ飾ります!!
2014年01月14日
タロとジロの日
ヤーマン。バナナマフィンだす。
本日 1月14日 は「タロとジロの日」なんだそうです。
タロとジロといえば「南極で置き去りにされるも1年後に奇跡の生還を果たした」ということで有名ですが、この生存が確認された日が、1959年(昭和34年)の1月14日であったことから、「タロとジロの日」が制定されたようです。
で
ワンの世代だと、この「タロとジロの話」は有名で、知らない人はいないと言っても過言ではないと思いますが、ワンは、何故この「タロとジロの話」を知っているのか?記憶にないのです。
ワンが忘れているだけなのかもしれませんが、学校の授業で出てきた記憶もないし、道徳の時間に習った記憶もなくて・・・。「いつのまにか、なぜか、知っていた」というのが正直なところなんですね。
というわけで、なぜワンはこの「タロとジロの話」を知るようになったのか、ちょっと推理してみました。
すでに小学校の高学年の頃には「タロとジロ」を知っていたワン。ということはそれ以前に、何かしらのタイミングで知識を得たことになり、そのキッカケとして考えられるのは 1.親から教えられた、2.友達や先輩との会話の中で知った、この2つが一番可能性が高いのかなあ?と思います。でも、ここまでは考えられるのですが、そこからハッキリとした答えは導き出せないのですね。記憶が全くないのです。
でも、記憶がないからといって、それが問題であるか?というとそうではなくて、逆に、こういうことが大切なのかな?と思っているのですね。いつ、どのようにして教えられたのか知らないけれども、いつの間にか習得していた。・・・それはたぶん、親から教えられたことが一番大きいんだろうと思うのですが、それは自分にとって一生モノになっているのだろうと思います。
「タロとジロの話」のほかにも、このテの話は色々あるような気がします。それは、時代の流れによって学校でも教えられることもあるかもしれません。またプロパガンダ的に使われた歴史もあるかもしれません。そして、実際の話と伝わっている物語で内容が違っていることもあるように思えます。
そんな色々な要素がある中でも、きちんと伝えなければいけない「物語の核」があると思うわけで、その部分を見極めて、それを正確に伝えていくことが大切なんじゃないかなあ?などと思ったりします。
そんなこんな考えると、大人になった今、もう一度見てみたいなあと思ったのが、こちら。高倉健さん、激シブでしたね。


南極物語 [DVD]
一方、ワンはドラマの本放送は見逃していたのですが、最近のお子さんは、これで「タロとジロの存在」を知ってるかもしれませんね。


南極大陸 DVD-BOX
てなわけで、近日中に制覇したいと思います。
したらば。
本日 1月14日 は「タロとジロの日」なんだそうです。
タロとジロといえば「南極で置き去りにされるも1年後に奇跡の生還を果たした」ということで有名ですが、この生存が確認された日が、1959年(昭和34年)の1月14日であったことから、「タロとジロの日」が制定されたようです。
で
ワンの世代だと、この「タロとジロの話」は有名で、知らない人はいないと言っても過言ではないと思いますが、ワンは、何故この「タロとジロの話」を知っているのか?記憶にないのです。
ワンが忘れているだけなのかもしれませんが、学校の授業で出てきた記憶もないし、道徳の時間に習った記憶もなくて・・・。「いつのまにか、なぜか、知っていた」というのが正直なところなんですね。
というわけで、なぜワンはこの「タロとジロの話」を知るようになったのか、ちょっと推理してみました。
すでに小学校の高学年の頃には「タロとジロ」を知っていたワン。ということはそれ以前に、何かしらのタイミングで知識を得たことになり、そのキッカケとして考えられるのは 1.親から教えられた、2.友達や先輩との会話の中で知った、この2つが一番可能性が高いのかなあ?と思います。でも、ここまでは考えられるのですが、そこからハッキリとした答えは導き出せないのですね。記憶が全くないのです。
でも、記憶がないからといって、それが問題であるか?というとそうではなくて、逆に、こういうことが大切なのかな?と思っているのですね。いつ、どのようにして教えられたのか知らないけれども、いつの間にか習得していた。・・・それはたぶん、親から教えられたことが一番大きいんだろうと思うのですが、それは自分にとって一生モノになっているのだろうと思います。
「タロとジロの話」のほかにも、このテの話は色々あるような気がします。それは、時代の流れによって学校でも教えられることもあるかもしれません。またプロパガンダ的に使われた歴史もあるかもしれません。そして、実際の話と伝わっている物語で内容が違っていることもあるように思えます。
そんな色々な要素がある中でも、きちんと伝えなければいけない「物語の核」があると思うわけで、その部分を見極めて、それを正確に伝えていくことが大切なんじゃないかなあ?などと思ったりします。
そんなこんな考えると、大人になった今、もう一度見てみたいなあと思ったのが、こちら。高倉健さん、激シブでしたね。

南極物語 [DVD]
一方、ワンはドラマの本放送は見逃していたのですが、最近のお子さんは、これで「タロとジロの存在」を知ってるかもしれませんね。

南極大陸 DVD-BOX
てなわけで、近日中に制覇したいと思います。
したらば。